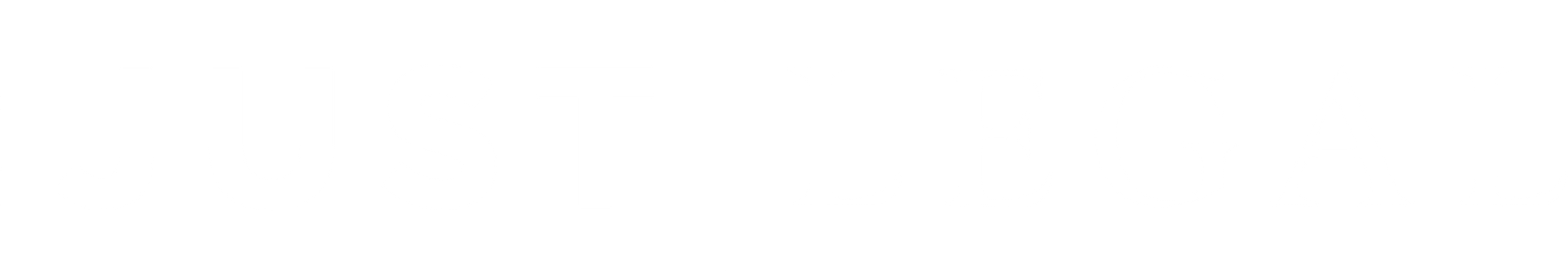Just Legalインタビュー: SBC メディカルグループ 岡本高太郎弁護士(53期)
トップ・ローファームでパートナーとなり、その後、企業内に身を置き、現在はナスダック上場企業における法務部長として法務機能強化に携わる――。一見すると、計算された戦略的キャリアのようにも思われますが、ご本人はそれを「結果的にそうなっただけです」と静かに笑います。

「目の前にあることをその都度必要だと思ってやってきただけです。あとから見れば、結果的につながっていたのかもしれません。」
岡本弁護士が法曹を志したのは学生時代のこと。「知的に面白く、人の役に立ち、専門性のある仕事に就きたい」と考えたとき、法律に興味を持つ。
キャリアのスタートは、2000年代はじめの大手四大法律事務所。人数はまだ少なく、昭和の香りが残る環境で、学びの多い日々を過ごしました。クロスボーダーM&Aや複雑な紛争案件、英文契約書のドラフティングなどを少人数かつ短時間で、人間の限界に挑むのかと思うようなチャレンジも経験をされたそうです。
「多くの案件を担当することで、弁護士としての土台を一つひとつ築いた感じですね。契約を構造から理解する力、調査力、文書をきちんと書く力。それらの基礎が、後々の現場でいきてくるのですが、そのときはとにかく必死なだけでしたね。」
「パートナーになった」その先を考えたとき。
しばらくするとパートナーに昇進され、外から見れば順調なキャリアです。しかし、そのポジションにとどまることは選択していません。
「当時としては、法律事務所を出るという選択は珍しかったと思います。ただ私は、“企業が、ビジネスが、どんな力学で動いているのか”を内側から自分の目で見たい気持ちが強かったです。」
トップファームからトップ企業アマゾンジャパンのインハウスへ。その後ブティックファーム2所、スタートアップ企業1社を経て現在は急成長中の医療グループで、法務責任者を務めている。どのような考えがあって決断してきたのでしょうか。
「緻密な戦略のもとに動いたというより、必要に応じて自分のいる場所を見直してきた、という感覚の方が近いかもしれません。」
評価よりも、手応えのある現場を選んだ?
「もちろん周りの評価も気になりますが、それよりも、自分がやっていることに意味があるかどうか、誰かの役に立てているかを大事にしてきたんだと思います。」
現職の美容医療に対する“正直な”第一印象とは?
「実は少し偏見のようなものがありました。美容医療って、世の中の誰もが使うものではないし、なんとなく『特殊な人が利用するもの』という先入観があって……。正直、あまりピンとこなかったというのが本音です。」
入社前は、美容医療という業態自体に対する理解も限定的だったという。
「たとえば鼻の形を変える、輪郭を整えるといった手術は、どこか別世界の話だと感じていた部分もありました。」
それでも飛び込んだ理由と「違和感のなさ。」なぜその世界に入ることを決めたのか。
「正直、多少の不安はありました。でも、会社の成長性や経営陣の発信を見て、“ちゃんと会社として事業をやっている”という感覚が伝わってきました。そこが最終的な決め手でした。」SBCメディカルグループは、コーポレート部門の組織基盤を強化する過渡期。メガバンクやコンサルティングファーム出身など、外部からキャリア豊富なエキスパートが次々と集まり、経営体制の厚みも増していました。

苦楽を共にしたコーポレートメンバーと
実際に入社してみて最も印象的だったのは、社内で働く人々が想像以上に“普通”であったということです。ここでいう“普通”とは、決して平凡という意味ではなく、誠実な医療経営を支援するという強い使命感と情熱を持ち、日々の業務に真摯に取り組む姿勢を備えた人たちでした。それまでの私は、美容医療業界に対する世間のイメージや偏見を、知らず知らずのうちに自分自身の中にも取り込んでしまっていたのだと痛感しました。そして同時に、こうした偏見を打破し、彼らと共に正しい姿を社会に伝えていきたいという思いが芽生えました。
入社後に感じたギャップと、新たな視点。
「実際に入って最も驚いたのは、業務の幅広さですね。」
法務・労務・情報セキュリティ・海外展開・M&A――。それらをすべて、ほぼ一人で支えている。
「美容というイメージだけでこの会社を見ていたら、絶対にわからないと思います。むしろ“医療法人”や“ナスダック上場企業”という側面のほうが、毎日の仕事には大きく関係しています。」
また、近年では消費者のニーズが外科的手術から「美容皮膚科」や「スキンケア」にシフトしつつあるという。
「皮膚科領域になってくると、もはや一般的な医療や生活習慣の延長に近くなる。しみ・そばかす治療なんて、もう“特別なこと”ではなくなっています。」
弁護士として、この業界で価値を出せる理由
この業界には、まだまだ法務人材が少ない。法令遵守はもちろん、ルールの整備やガバナンス対応においても、外部弁護士ではなく“中の人”がやらなければ動かない局面が多いという。
「それなりの規模なのに、誰も担ってこなかった領域がたくさんある。そこに自分が入る意味は大きかったと感じています。」
“わからなさ”の中に飛び込む価値:先入観の裏にあった“成長の場”
美容業界に対して、岡本弁護士が感じていた違和感やためらいは、ごく自然なものである。だが実際に入ってみて気づいたのは、「先入観は、情報不足から生まれることが多い」ということだった。そして今では、美容という分野が持つ“成長性”と“社会的ニーズ”の大きさを、日々の業務を通じて実感しているという。
「すごく特殊な場所に来た、とは思っていません。ただ、他の人があまり見ようとしてこなかっただけで、実はちゃんと組織として機能していて、法務が必要とされている世界なんだと、今は思っています。」
M&A、労務対応、情報セキュリティ、海外子会社の法務支援、上場企業としてのガバナンス体制の整備まで、担当範囲は多岐にわたります。入社当初から「何でも屋」のような立場だったが、そのなかで手触りのある仕事をひとつずつ積み上げてきたという。
「最初は、正直ここまで幅広くなるとは思っていませんでした。でも、気がつけばやれていた。そういう状況に置かれたからこそ、自分の力を試す機会になったのだと思います。」
「飛び込んだ」のではなく、「組み立てながら進んだ」
ご自身のキャリアを振り返って、「無謀な挑戦をしてきたつもりはない」とおっしゃいます。一つひとつの選択は常に慎重で、丁寧だったと。道筋が完全に見えていなくても、立ち止まるのではなく、組み立てながら少しずつ前に進んできた。まさに、それこそが岡本弁護士の強さなのかもしれません。
「キャリアに“正解”はないと思います。でも、自分がしてきた選択に納得できるか。それだけは、ずっと大切にしてきたことです。」
弁護士という職業には、慎重であること、確実であることが求められる場面も多くあります。その一方で、ときにその特性が、柔軟さや“新しい風景”を遠ざけてしまうこともあるかもしれません。
少しずつ道を変えながら、自分自身で“次のかたち”を見つけてこられた歩みは、これからキャリアを考える多くの法務人材に、静かな示唆を与えてくれています。