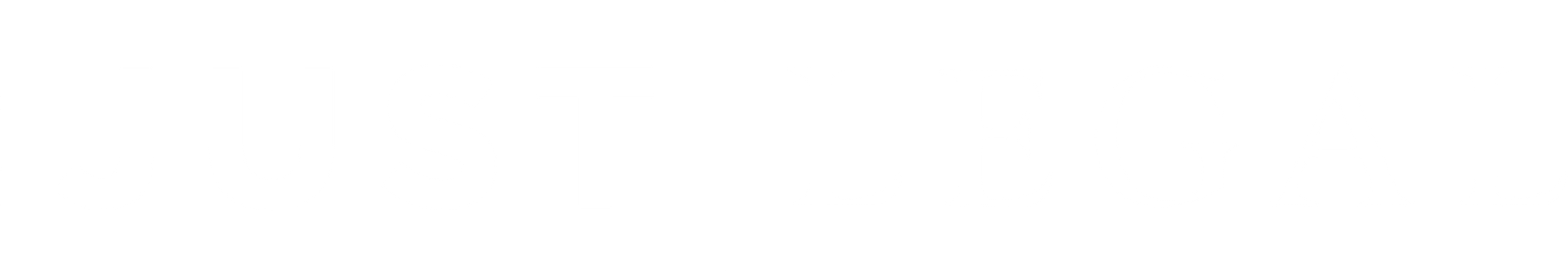卓越したアドバイスを提供するための探求と挑戦 インタビュー:今仲翔弁護士
卓越したアドバイスを提供するための探求と挑戦
インタビュー:今仲翔弁護士
AI時代も本質的に弁護士に求められる能力は変わらない
今仲弁護士は「弁護士に求められる力はAI時代においても変わらない」 と強調します。条文知識や膨大な判例検索は法的課題を解決するための手段であり、目的ではありません。AIがどれほど進化してもなお揺らがないもの、それはクライアントに寄り添い、状況を把握し、的確な言葉で説得し、交渉や紛争を解決する能力です。
大手四大事務所で数多くのM&A案件を担当した経験からも、交渉の現場で相手を動かすのは「クライアントや交渉相手の気持ちを汲み取る能力」であることを痛感してきたといいます。
「AIは大量の情報を処理できますが、クライアントや交渉相手の意思決定を左右するのは、最終的には人間の言葉。この原点は今後も決して変わりません。」
このような考えを持つようになった大きな契機が、ニューヨークの法律事務所での研修経験でした。現地のトップ弁護士たちは徹底的に調査を行いながらも、クライアントへのアウトプットは驚くほどシンプル。
「何時間ものリサーチを積み上げた結果、法的な問題がないと確信できた場合には余計な留保をつけずに結論のみをシンプルに伝える。クライアントとの信頼関係が築けていることが前提ですが、無駄のないアウトプットが印象的でした」
弁護士としては、「何をどのように調べたかも含めてなるべく丁寧に説明する」ことが良いと考えていました。もちろんそれ自体は誤りではないのですが、ニューヨークのロイヤーたちは徹底した下準備と同時に、デリバリーにおいても徹底してクライアントセントリックを貫いていました。クライアントの真の要望や信頼関係まで考えると「ロイヤーの回答を確認する時間を減らすこと」がベストなアドバイスとなることもあるのだなと大変勉強になったといいます。
ニューヨークでの経験は、さらにもうひとつの気付きを促しました。自分が「正しい」と信じてきたやり方も、必ずしも普遍的な正解ではないということです。難しい論点について徹底的に調べた結果、結論の報告は一行でというやり方を見たとき、彼は「自分の枠組みに固執せず、柔軟に考え抜くことの重要性」を学んだのです。
この二つの学びは、その後のキャリアの意思決定にも深く影響しました。「もっと優れた価値提供の方法はあるか」と常に問い直し、新しいフィールドに踏み出すことへの源泉となりました。
________________________________________________________________________________________________________________________
現状維持ではなく、敢えて挑戦する理由
大手四大法律事務所でパートナーに昇進したと聞けば、多くのエージェントや同業者は「この人は成果を出した」と考えるでしょう。もう移籍や転職はなく、そのまま事務所でキャリアを全うするはずだと。実際、これまで四大事務所でパートナーになった後に、他事務所へ移籍したりインハウスへ転身した弁護士は少数です。
しかし今仲弁護士は、その座をあえて手放し、外へ出ました。
その理由は二つ。
- 「30年間同じことを同じ場所で続けて差別化できるのか」という分析。
- 「未知の世界を経験したい。ロイヤーとしての可能性を広げたい」という好奇心。
差別化の壁
パートナーになった後も以後30年以上は第一線で働き続けることが想定されます。しかし、例えばM&Aという分野において、同じ環境で案件を積み重ねることで他の弁護士との差別化を図ることは難しいのも事実です。「このまま同じ環境で業務を続けて、本当に30年後に自分は第一線に残れるのか」——その問いが大きく響いたといいます。
未知への好奇心
さらに彼を突き動かしたのは、好奇心でした。パートナー就任の直前、出向先で出会ったグローバルで活躍する経営者たち。彼らがリーガルに求めるものは単なる案件処理にとどまらず、リーガルのスキルを使って「いかに経営を推進するか」という視座でした。その高い要求水準に触れたとき、法律家として成長するには様々な道があることを実感したのです。
「弁護士として個の力を磨くことは当然大切です。ただ、個の力を磨くための手段は様々です。自分は、未知のフィールドに飛び込み、自分の可能性を広げることに挑戦したいと強く思いました」
事務所を離れる決断は、多くの人にとって意外に映ったかもしれません。しかし今仲弁護士にとっては大きな躊躇はありませんでした。
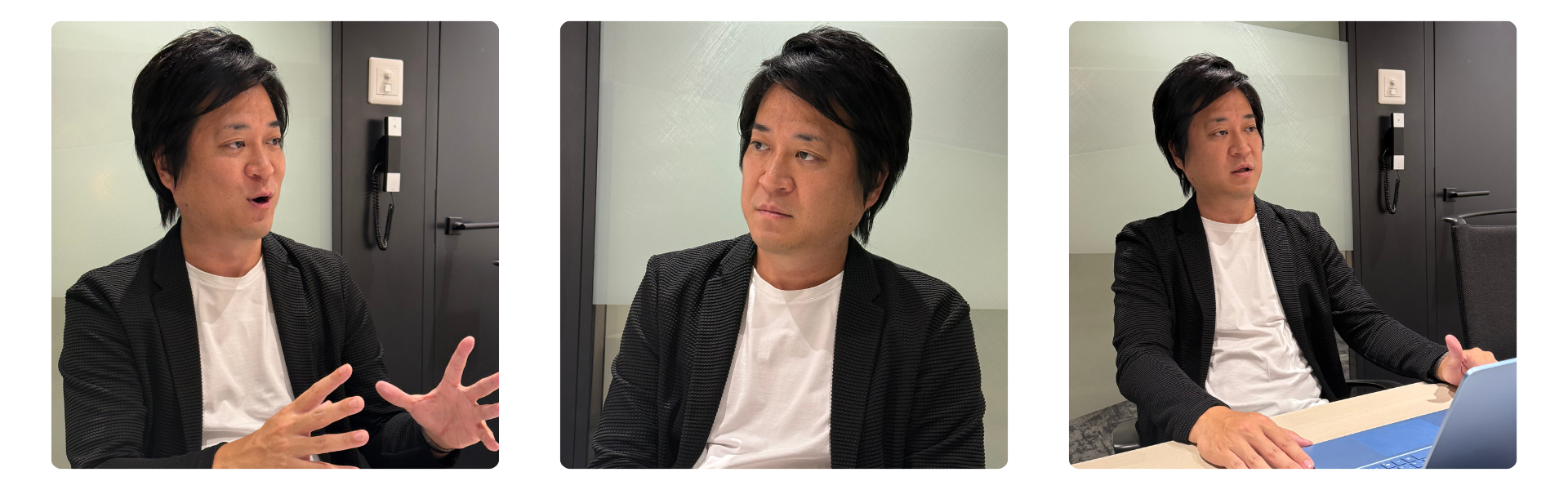
________________________________________________________________________________________________________________________
プレイヤーからマネジメントへ——経営視点の獲得
今仲弁護士が次に挑んだのは、当時すでに上場を果たしていた成長企業、Medleyでした。ジェネラルカウンセルという立場で迎えられた彼を待ち受けていたのは、従来の弁護士キャリアとはまったく異なる挑戦でした。
事務所時代、彼の役割は「案件を正確かつ迅速に処理すること」に集約される、いわばプレイヤーとしての能力を磨き抜くものでした。しかしジェネラルカウンセルという立場で必要とされたのは、個の力ではなく、法務機能をどう整備・発展させ、経営の推進に資する法務組織を作り上げるという視点でした。
そこでは「どんな人材をどう採用し配置すべきか」「全社的なリスクの顕在化をどう未然に防ぐか」「他部署とどのように連携し、経営陣の一員として会社を経営していくか」といった問いが日々突きつけられました。単なる案件処理の延長ではなく、経営の一部を担う責任そのものだったのです。
「自分が優秀なプレイヤーであるだけでは不十分なのです。究極的には自分がいなくても組織が回る仕組みをつくること。それがマネジメントの本質だと気づかされました。」
Medleyでの経験によって、今仲弁護士は「個人として成果を出す」から「仕組みを通じて組織全体の価値向上に貢献する」という発想転換を余儀なくされました。これは、弁護士として培ってきた視点を超えて、経営を担うプロフェッショナルとしての新たな地平を切り開く 転換点となったのです。
Medleyに在籍していた3年半の間、急激に変貌を遂げるベンチャー上場企業の成長をサポートすべく法務部も大きく変化しました。特筆すべきは、今仲様がジェネラルカウンセルとして急成長を続ける企業の経営陣を務めたことだけでなく、同時進行で法務部の組織構築を行い、組織を育てたことでしょう。
________________________________________________________________________________________________________________________
なぜ独立という道を選んだのか
今仲弁護士のキャリアの特徴は、一般に「到達点」とされる地点を決してゴールと捉えないことにあります。大手事務所でパートナーに昇進することも、上場企業でジェネラルカウンセルを務めることも、多くの弁護士にとっては輝かしい到達点と見なされます。けれども今仲弁護士は次に独立という道を選びました。
「肩書きや立場も大切ですが、そこで何を経験し、次にどう生かすかが重要だと思います。私の場合、企業内法務の経験を通じて新たなニーズが見えて、そのニーズに応えていくためには独立が一番良いと判断しただけです。」
ジェネラルカウンセルとして経営陣と向き合う中で、「どのような人材を採用すればよいか」「ジェネラルカウンセルとは何をすべき存在なのか」といった根本的な問いに直面し、答えを得られず苦しんだ経験があります。同じ立場の同僚、先輩がほとんど存在しないため、法律事務所の弁護士に相談することもできませんでした。
また、日本企業は市場のグローバル化の影響で、法務、コンプライアンス、ガバナンス機能のアップデートが必要で、これは法的知識というよりは、より大きな視点からの経営経験がないと解決できません。日本企業の競争優位やリスク管理を考える上でも、当該分野におけるエキスパートがいることは重要です。
「自分がかつて感じた法務責任者の孤独と難しさ」を活かして他の人をサポートしたい。また、弁護士業務の提供だけでなく、法務・コンプライアンス・ガバナンス機能の立ち上げや組織運営をサポートして欲しいという企業のニーズがある、との確信とともに、独立という道を選ばれました。
________________________________________________________________________________________________________________________
若手へのアドバイス「異なる環境での経験は財産となる」
「迷うほど魅力的な選択肢があるのであれば挑戦してみることが良いのでは。AI時代においてもどれだけ幅広い経験をしているかがより重要になる。やり直しはいくらでもできる」
環境を変えることにより得られる経験値や人脈のメリットは大きいです。慣れ親しんだ環境を離れるには勇気がいります。先輩やメンターからの慰留もあるでしょう。ただ、時代は変わり続けています。同じ組織にとどまり続けることも、リスクになる可能性もあります——今仲弁護士はそう問いかけます。
事務所からインハウスへ、そして独立へ。自ら挑戦と変化を重ねてきたからこそ、選択肢を閉ざさずに動くことの意味を語ることができるのでしょう。キャリアは積み重ねるだけでなく、ときに「手放す」ことによって広がる。そうした柔軟さを持つ人ほど、より広い人脈と厚みのあるスキルを獲得し、手応えのあるキャリアを築いていけるのかもしれません。